【令和5年 岸和田だんじり祭 and 岸和田城】
2023年9月17日(日)、午前中 宮入り、午後曳行、見に行ってきました。
相当な人出と、熱気でした。地車が行き過ぎるのは一瞬です。
地車(だんじり) 総けやき造り 重量:約4トン 高さ:3.8m 長さ:4m 幅:2.5m です。
曳き綱:長さ100m~200m 500人~1,000人で曳かれます。
地車(だんじり)大屋根の最上部の『大工方』が団扇を持ち舞いを舞うほか、進路の発見・調整を行います。
『大工方』はだんじりの司令官としての役割があり 両手に持つうちわや動きで、各持ち場に指示を出しています。
岸和田型だんじりの製作費用は平均1億円以上もする走る芸術品とのことです。
最大の見せ場は、重さ約4トンある「だんじり」を勢いをつけたまま直角に向きを変える「やりまわし」です。
岸和田市は中でも有名ですが、堺市、忠岡町、貝塚市、泉大津市 等、泉州各地には地車祭があります。
(和歌山・石山)
- 南海電車 特急サザン
- 南海電鉄 岸和田駅前
- 南海電鉄 岸和田駅前
- 岸和田天神宮神社 宮入り
- 若人が練習
- 先頭です。注意喚起
- 早いスピードで地車を曳きます
- 屋根の上の『大工方』が指示
- 屋根の上の『大工方』が指示
- DJポリス「警備現場広報」
【岸和田城】
岸和田城の別称は「猪伏山千亀利城(いぶせやまちきり城」です。江戸時代には岸和田藩の藩庁が置かれていました。
城内、明智光秀公の肖像画(複製)展示があります。(光秀公の肖像画はこれのみの様です)
本物は岸和田市にある本徳寺所蔵、光秀公の位牌もあるとのこと、寺の開祖が光秀公の息子?との話もあります。
岸和田城は大坂城と和歌山城の中間地点にあります。南海電鉄本線車窓から間近に見える城です。(蛸地蔵駅~岸和田駅 の中間)
城主・岡部宣勝公は徳川家康公の妹の子で、通説では徳川御三家紀州藩・和歌山城の監視の意味もあったとされています。
和歌山市~岸和田市 電車、車で約30分です。
- いぶせやま 猪伏山
- 大手櫓門
- 岸和田城
- 江戸時代に使用されていたとされる駕籠(かご)
- 阿弥陀如来坐像 具足
- 岸和田城 模型
- 天守より神戸・六甲山方面











































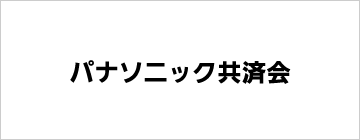

この記事へのコメントはありません。