
自称「バレーボールと資格チャレンジが趣味」のうんちく大好きなおじさんです。
支部のご好意で「うんちくを披露しても良い」との了承を得て、支部HP内に1ページをいただくことになりました。
まあ、役に立つかどうかはさておき・・軽ーく読み流していただけたら嬉しいです。
うんちくおじさん
※編集者記:以下、投稿の逆順(最新の投稿が上側)に掲載しています
⑥税額控除
みなさんは多少なりとも所得税や住民税を払ってると思う。
税金を計算する時には社会保険料や地震保険などの控除を収入から引いてから税額を計算するよね。
さてこの計算した税額から直接差し引きする税額控除って知ってるだろうか。
例えば次のものがある。
①(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
②認定NPO法人等寄附金特別控除
③公益社団法人等寄附金特別控除
このうち①は若い頃に住宅を購入して使ったって方が多いかもしれない。
②と③は例えば「国境なき医師団」とか「日本赤十字社」とか「大学法人」とかへの寄附である。
例えば10000円を寄附したとしたら
所得税で、(10000円−2000円)×40%=3200円が引かれ
住民税で、(10000円−2000円)×10%=800円が引かれる
世のために10000円寄附したのが世界の誰かに少しは役に立って、しかも税金が4000円返って来るって、なんか気持ちがいいと思わない??
⑤銀行の退職金プランの怖さ
ある銀行の退職金プランの内容である。
500万円以上
半分(250万円)は定期預金 利息 年7% (3か月満期)
半分(250万円)は投資信託
投資信託内容
①申込手数料:最大3.30%(税込)
②信託財産留保額 購入時0.1% 解約時0.5%
③信託報酬: 純資産総額に対して最大年2.20%(税込)
④その他の費用:
証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料
または税金、先物・オプション取引に要する費用
組入資産の保管に要する費用
投資信託財産に係る会計監査費用
実質的に投資対象とする資産の価格に反映される費用
(各々必要な場合は消費税等を含む)など
まず定期預金だが年7%で3か月満期だから、
3か月利率=7%×(3/12)=1.75% これに税金が20.315%かかるから
ほんとの利率=1.75%×(1-0.20315)=1.39%(金額で34,750円)
年7%とか言って客をおびきよせてるけど、ほんとの利率は1.39%しかない!!・・
ところが投資信託でいきなり手数料3.4%引かれるから(金額で▲85,000円)
最初の1年終了時に投資信託の成果がプラスマイナス0だとしたら
1年修了時にすでに収支は、34,750円−85,000円=▲50,250円になる。
そう銀行はこの手数料欲しさに「退職金プラン」というものを販売している。
そして運用中はずっといろんな費用(上記の㈫㈬)を引かれ続ける。
よっぽど運用成績がよくないと資産は減る一方である。
だからほとんどの人は損してるという声が聞こえる・・(恐ろしい・・)
④投資信託の特別分配金の怖さ
投資信託の「特別分配金」って知っているだろうか。
それは「分配する金額ありきで、運用成果を超えても分配してる」もので、つまり運用で儲かってなくても「特別に分配金を出すよー」ってもの。
例えば、運用開始時に1000万円で契約してその年の運用は5%の損失となったとすると、当然950万円に目減りする。
でも契約で年間で50万円を「特別分配する」ってしてたら、その950万円から50万円を支払ってしまう。
客としては「やった年間50万円ももらった!」って喜ぶかもしれない。
でも、この時点で元本は差引950万円−50万円=900万円になってしまう。
この特別分配金50万円というのは、預けたお金を取り崩してるだけ。
当然元金が減るから次の年はさらにすばらしい運用をしないと50万円の分配はできない。結果、毎年どんどん元金が減っていく。
タコが自分の足を食べるのをイメージして、こんな投資信託を
「タコ足分配」「タコ足配当」と隠語で呼んでいる。
こんな投資信託が世にまかり通ってるんだよー!!(・・怖ろしいねー)
③配偶者居住権
2020年4月から新設された「配偶者居住権」って知ってますか?
不動産の権利を住む権利(居住権)と持つ権利(所有権)に分けて相続させるというもので、この制度ができたことで「亡くなった方の自宅に配偶者(妻)がずっと住み続けることができる」ってすばらしい制度です。
例えば、亡くなったAさんの遺産が2000万円の家と2000万円の預金とします。
妻(Bさん)と娘(Cさん)の二人が(仲のよくない)相続人とします。
①今までの制度でしたら、Cさんが「母さん(B)に2000万円の家をあげるから、私(C)は2000万円の預金をもらうわよー!」とか主張したら
妻(Bさん)は家に住み続けることができますが老後の資金が無くなってしまいます。
もし預金が500万円しかなかったら相続のために家を売らないといけなくなる事態になるかもしれません。
②新しい制度では両者の相談で、妻(Bさん)の一生の居住権評価額を500万円、家の所有権評価額を1500万円という風に決めることができます。
そして預金額をうまく分けると、BさんとCさんの相続額は、
Bさんの相続=居住権500万円+預金1500万円=2000万円
Cさんの相続=所有権1500万円+預金500万円=2000万円
と仲良く同額で平等に分けて、Bさんは老後の資金と一生家に住む権利を確保することができます。
なお、Bさんが存命中にCさんが家を売ることもできますから、Bさんは「居住権を登記」しておいた方がいいとのことです。
いかがでしょうか?「うちは心配いらないよーー!!」って思うかもしれませんが、「必要だから生まれた制度」ってことをよーく考えてくださいねーー。
②相続不動産の3000万円控除
自分で住んでる家を売ると売却益から3000万円の控除があるって知ってる人はけっこういるんじゃあないかと思う。
そして、相続した不動産の売却益についても同様に3000万円の控除制度がある。
ただし、ちょっと条件は厳しいんだけど、これを利用するかどうかで何百万円も税金が変わるから知ってて損はない。
別居の親が亡くなって住んでた家を相続した時に次の条件で売れば売却益から3000万円の控除ができる。
①昭和56年5月31日以前に建築された、戸建
②相続前に被相続人以外は住んでいなかった
③一定の耐震基準を満たす家、もしくは更地
④相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
⑤この制度は令和9年12月31日まで
例えば相続した家の売却益が3000万円だとすると、この制度を使わなければ税金は約2割だから600万円だけど、この制度を活用すると税金が0円になる。
けっこう手続きがややこしいから司法書士に相談しよう。
①養子縁組相続
養子縁組は相続税を減らすための簡単で有効な方法と言われてる。
また遺産を渡したくない人への相続遺留分を減らす手段としても有効である。
相続税を計算する時の控除額は次の式で計算する。
控除額=3000万円+600万円×相続人の人数
さて夫Aの遺産が5600万円あり、相続人が妻Bと子供2人(CとD)とする。
そしてDさんは暴力を振るうので遺産を残したくないので遺言書でBとCだけに相続させると書いたとする。
この場合 控除額=3000万円+600万円×3人=4800万円
遺産5600万円-控除額4800万円=800万円に相続税がかかる。
ここでDには「相続遺留分」があるので次の額を受け取ることができる。
5600万円×1/2×1/2×1/2=700万円
次にAが子供Cの妻Eを養子縁組したら相続人は4人になるので
控除額=3000万円+600万円×4人=5400万円
遺産5600万円-控除額5400万円=200万円だけに相続税がかかることになる。
そしてDの「相続遺留分」は次のように少なくできる。
5600万円×1/2×1/3×1/2=467万円
子供の嫁さんEが介護をしてくれて「とってもいい人」だったとしても、孫がいなくて何も対策せずに子供Cが先に亡くなっちゃたら子供の嫁さんEには遺産が残せなくなるから、そういうケースでも「子供の嫁さんを養子縁組する」ってのはいい手段だよー。
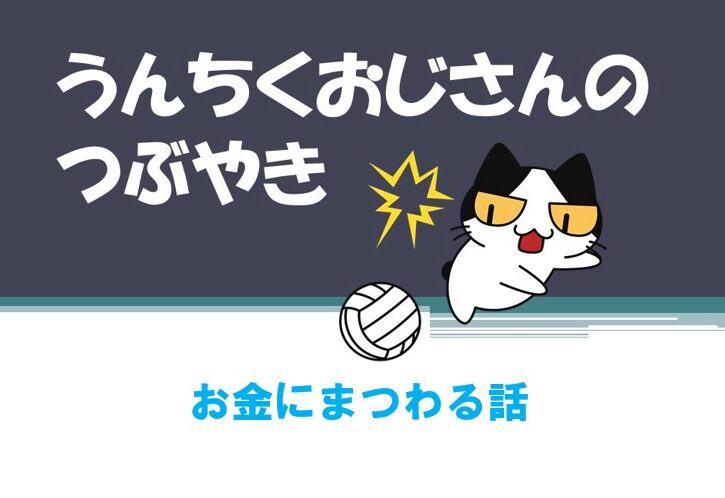








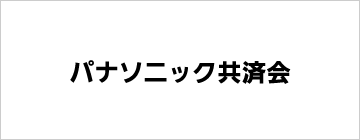

この記事へのコメントはありません。