画像はクリックすると拡大します。「<」や「>」が出たときは、このクリックで連続表示します。動画は左上の「タイトル名」をクリックすると、直接 YouTube につながります。
<第99回例会> 釣釜に棚は旅箪笥で稽古 2025.03.12(7人参加)
次回開催予定:2025.04.13(日)
3月になると少しずつ暖かくなり、炭火から釜を少し離すように、天井から釜を釣り下げる「釣釜」でお点前をします。釣釜の稽古は 3,4月にしますが、春の訪れが感じられ少し特別感がありウキウキしてしまいます。
また、今回使う棚は旅箪笥(たびだんす)です。旅箪笥はその名前のとおり持ち歩ける携帯用の木地製の棚で、千利休が豊臣秀吉の小田原の陣に従った際に考案したといわれています。
その構造は地板に水指、中棚に棗(なつめ)と茶碗を入れ、上棚の切り込みに柄杓(ひしゃく)を掛けるようになっており、野点(のだて)などにも用いられます。








<第98回例会> 2月は大炉(逆勝手)のお点前 2025.02.12(8人参加)
次回開催予定:2025.03.12
ここしばらくは全国的に寒波が到来。正に極寒の二月のお点前といえば大炉(逆勝手)です。すでに先生が用意してくださった逆勝手のしつらえに、皆さん「どうしよう…」とオロオロ、ドキドキでした。
まずは大炉の場合を考慮して、先生自ら逆勝手の濃茶点前です。左右逆を感じさせないなめらかな運びにうっとりでした。その後、IMさんが薄茶で逆勝手に挑戦、本勝手と異なるところ、同じところ、足の運びなどを確認しました。
逆勝手の締めはKMさんの流れるような濃茶点前、茶室には練られた豊満な茶の香が広がり、全員がおいしい濃茶をいただくことができました。コロナ騒動により濃茶は各服で稽古をしてきましたが、今回は久しぶりに回し飲みでいただきました。各服とは違う濃茶の奥深い味わいを改めて感じることができました。
それにつけても皆さん濃茶の茶碗を拭く小茶巾の扱いがうまくいきませんでした。「一度拭いたところを戻して拭いてはいけません。練習が必要です」と先生のおしかりの一言。小茶巾のたたみ方から復習しましょう。
本勝手で筒茶碗使用の平点前も稽古しました。筒茶碗は口が小さいので点てにくく、その人の手の大きさに合わせた工夫が必要です。茶巾は「い・り」と拭いた後、手前を人さし指と中指でつまんで持ち、反転させて茶碗の縁にかけます。新しい会員さんも頑張っています。
帛紗さばきの「真」「行」「草」の稽古もしました。日頃のお点前は「草」でしていますが、今日は本にもネットにもない「真」「行」のさばき方を教わりました。
まずは帛紗を正しく折りたたみ、懐中したり腰につけたり、「草」の基本をきっちり覚えることが必要です。「真」も「行」も難しくて短時間で覚えることはできませんでしたが、これから稽古を重ねたいと思います。










<第97回例会> 先生の「唐物」点前拝見 2025.01.08(8人参加)
次回開催予定:2025.02.12(水)
2025年の初稽古は、初回からご指導いただいている大友先生の「唐物(からもの)」点前で始まりました。一同、お点前を静かに拝見しました。「唐物」は「四ヶ伝(しかでん)」と言われる中級クラスの点前の一つで、テキストはなく口伝で教わる点前です。
主に中国から伝来した由緒ある陶磁器の茶入れの「唐物」を使い濃茶を練ります。大切な唐物茶入れですので、茶杓は手元に節があるものを用い、それぞれの道具も丁寧に扱う所作が求められます。また、お菓子も 2種類の主菓子と水菓子(果物)1種になります。本年初回の大友さんが練られた濃茶は格別でした。
続いて会員の一人が「四ヶ伝」の一つの「台天目」の点前を披露しました。天目台という道具に天目茶碗を載せていただくお点前で、茶杓は木製ではなく象牙製を使います。








記事がよければ「いいね!マーク」のクリックをお願いします


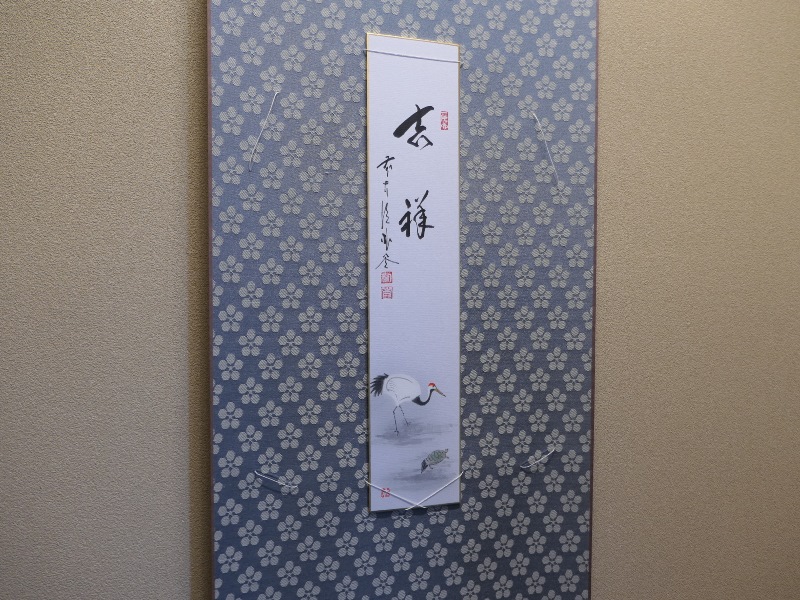

この記事へのコメントはありません。