 12班 岩﨑 和隆 さん
12班 岩﨑 和隆 さん
先人の旅我もするなり五月晴れ(和隆)
2024年5月にずっと温めていた自転車旅行~奥の細道~にやっと出発できました。新型コロナ禍で3年、膝の手術で1年、合わせて4年遅れです。体力低下が心配な状況で、どこまで頑張れるかの挑戦です。
5月14日、自転車を担いで最寄りの駅まで徒歩で出発しました。朝の通勤時間を避けて乗ったつもりが結構混んでいました。新大阪から新幹線に乗車します。指定された大型荷物置き場に自転車は入りませんでした。仕方ないので、車両最後尾の背面スペースに置くしかありません。そこには中国系の家族連れが既に座っているけど、ことの背景を説明し、理解を得て、背面スペースに置けました。助かりました。
東京駅に11時過ぎに到着。何年ぶりかを忘れる程の久しぶりの東京です。日本橋側に出て、交番前で自転車を組立作業すると警官が迷惑そうな顔。で、横裏にずれて作業を終わらせます。12時35分いよいよ旅の始まり、まずは日本の道路元標の日本橋へ。写真2は旅の始まりに旅行中の高校生に依頼して撮ったものです。写真3が自転車で初めてこの地に立った、自転車行脚の始まりの1999年の私です。この時は通りがかりのOLさんに撮影を依頼。写真からもずいぶん年数がたちましたね。
次は深川へ。手書き地図とGoogle Mapを頼りに海辺橋に向かい、たもとの採茶庵の芭蕉像。ここでも通りがかりの男性に撮影を依頼。親切な方で折角だから引きではなくアップ撮影で撮りましょうとこの写真4、5です。
次は浅草寺(写真6)へ。ここでとてもこのページでは紹介できそうにない人物~下駄履きに上半身は女装で下帯だけの男性~に遭遇。流石に、東京は多様性の町であると実感しました。
次は芭蕉稲荷神社(写真7)を巡り、千住大橋のたもと芭蕉さんの出発の地「矢立初めの地」に向かいます。私もこれから2400㎞の旅を始める決意を固めました(写真8)。
ここで芭蕉は~行春や鳥啼魚の目は泪(ゆくはるやとりなきうをのめはなみだ)~と感極まって、惜別の句を詠んでいます。
初日の目的地の草加駅には予定より約1時間遅れて到着。フロントにお願いして自転車を部屋に持ち込みます。予めホテルに送ってあった荷物を輪行バッグに入れて自転車にセットします。これで、初日が終わりました。
- (写真2)日本橋にて
- (写真3)1999年同じ日本橋にて
- (写真4)採茶庵にて
- (写真5)採茶庵にて
- (写真6)雷門
- (写真7) 旅の無事を祈る
- (写真8)旅立ち
第2日、ホテルの朝食サービスをあきらめて、7時過ぎに出発。旧道日光街道(埼玉県道49号線)を進みます。途中芭蕉像(写真1)、曽良像(写真9、芭蕉像の道路反対側にある)や、壁画(写真10)を見て、芭蕉の旅姿を想像します。芭蕉は私よりも軽い装備だと感心します。越谷、春日部、古河をすぎて野木でトラブル発生。その重装備の自転車だからか、R4/日光街道で車に追い立てられ、急いで歩道に上がろうとしたときに歩道への小さい段差で自転車が転倒してしまいました。リアバッグで後加重になりフロントが浮きやすく、段差でフロントが上がって転倒しました。でも、お陰さまで自転車には特に異常はありませんが、左前腕の側面がちょっと擦り傷になっていました。まあなんとか無事でした。
今日の目的地小山駅に15時過ぎに到着。ホテルに直行して、変に疲れていたのか直ぐに寝ました。
第3日天気予報では夜中に雨が上がるとなっていましたが、5時起床時でも雨が降っています。だけど、部屋から外をのぞいたら、車のワイパーは動いていない、人も傘をさしていません。雨があがったかと思いましたが、1階におりて、外をみると雨が降っていました。通り過ぎる人は、傘あり、傘なしが混在してます。予報を見ると9時までの雨となっています。それで、とにかく準備だけは進めておいて、雨が上がるのを待ちました。ウェザーニューズの5分予報では9時半で雨がやむとあります。とにかく待機することにしました。そしたら、雨があがりました。というより、霧のような雨です、衣服を濡らしません。おもわず「ウェザーニューズ、すごいなあ」と声を上げてしまいました。フロントマンが驚いてこっちを見ています。直ぐに出発することにしました。
ホテルを出て、今日最初の場所は歌枕「室の八島」の大神神社です。どこが八島なのか分からず、宮司さんに尋ねます。確かに八つの島(写真11)でした。芭蕉の句碑もあったが、文字が読み取れない(写真12)。残念です。
次は日光です。鹿沼で昼食休憩の後、元気よく日光に向かいます。しかし、これが大変でした。日光への道は「日光例幣使杉並木街道」です。修学旅行での記憶通りに、両側が杉並木で気持ちがよいですが、ひょっとして熊が出没しないかと心配しながら、ずっと続くダラダラ坂を進みます。意外としんどかったです(写真13、14。写真14の道路とは少し離れたところに更に古い街道がある)。宿は昨日予約した日光駅近くの観光ホテルです。今回の旅行中で最も高額なホテルになりました。外人観光客でほぼ満室だとフロントは言います。とにかくダラダラ坂で疲れて、陽明門見学は明日に延期して、早く寝ることにしました。
- (写真11)分かりにくいが島が8つ
- (写真12)句碑
- (写真13)旧日光街道-1
- (写真14)旧日光街道-2
第4日、日光東照宮陽明門を見学です。出発の準備をすませてから東照宮に徒歩で7:20に出発しました。ところが、見学は9時からでした。とても待てないので、陽明門はあきらめて、芭蕉の句碑見学だけに変更。句碑(写真15)を見終わって東照宮陽明門前を向かうとすでに大勢の観光客が待機しています。ホテルに戻り、直ぐに出発。今日の目的地は栃木県大田原市黒羽で、途中那須神社に寄ります。源平戦の那須与一が扇を矢で射落すとき、「南無八幡大菩薩」と祈ったのがこの八幡宮/那須神社(写真16)です。ここには那須与一伝承館があるが入らず、参拝だけにして黒羽の宿に向かいました。
第5日、今日はホテルに連泊して、雲巌寺やら黒羽周辺の芭蕉ゆかりの場所を見学することにしました。まず雲厳寺(標高455m)までの上りです。日光のようにダラダラと最後まで上るわけではなく、ピークを過ぎれば下りで、到着直前に少し上るだけでした。雲巌寺(写真17)は古くて、威厳のあるお寺でした。この後、芭蕉の館(写真18、黒羽への途上で那須野原を越える馬上の芭蕉と曾良)→常念寺→西教寺→翠桃邸あと→余瀬の道標→玉も稲荷→犬追い物を見学して、ホテルに帰ります。しかし、雲巌寺では芭蕉が見学した「仏頂和尚山居跡」を見るつもりが、見逃してしまいました。残念です。仏頂和尚は江戸深川で芭蕉と交流があった方で、芭蕉はその何事にも執着しない生き方に憧れ、黒羽で最も訪ねたいところと出発時から思い募らせていたようです。
- (写真15)芭蕉句碑
- (写真16)那須神社
- (写真17)雲巌寺
- (写真18)芭蕉の館
第6日、今日は殺生石を目指します。黒羽を出て1時間ほどで黒磯駅に着き、今晩の宿にリアの荷物を預けて、身軽になって殺生石をめざします。旧道を走ると、本当にのどかな田舎の農村です。この道は日光に劣らず上りが続く道でした。10時過ぎ一軒茶屋のコンビニにつき休憩しました。再出発しましたが、すごい上りが続き、しんどくなって再度休憩。そして再出発したら、直ぐにイオウの臭いがきつくなりました。殺生石(写真19)に到着です。辺り一面イオウが匂っています。あちこちに白く黄色くイオウ噴出跡があります。ちょっと気分が悪くなり早々に宿に引きあげました。
第7日は、朝から雨なので、ホテルでじっと休んでいました。
第8日、今日は下野(栃木県)と陸奥の国境「白河の関」をめざします。東北/奥羽地方は、未だかって訪れたことがない未知の土地です。まず黒磯駅から黒田原を経由して芭蕉がよんだ「遊行柳(ゆぎょうやなぎ)(写真20、21)」を見ます。太い幹の柳が田んぼの中にぽつんと築山のようにありました。
ここで芭蕉は~田一枚植えて立去る柳かな(早乙女たちは一枚の田を植え終えて、次の田に移ろうとしていた)~と柳の木陰で詠みました。
この後に旧陸羽街道を北上し各地の一里塚(写真22)を見ます。この先に栃木と福島の国境の明神(住吉明神と玉津島明神、写真23、24)を参拝しました。いよいよ陸奥に入り、ちょっと感慨深いものがありました。そして、山中の道を迷いそうになりながら白河の関跡に向かいました。関跡には、芭蕉の句碑、白河関所、白河関の森公園などがあり、たくさんの写真を撮りましたが、残っているのはこの一枚のみ(写真25)。なんでか?一日走った後の疲れた頭で間違って消してしまったようです。もう二度と来れないと思うと悔しくて、がっかりです。
この後、白河市に向かいました。そこで、今回の旅で初めて東北のラーメンを食べました。縮れ麺のあっさりしたスープ(写真26)でおいしかったです。この旅の間中、なんで東北はラーメンが有名なんやろかと、ずっと考えてました。
- (写真19)殺生石
- (写真20)遊行柳-1
- (写真22)泉田の一里塚
- (写真23)住吉明神(栃木県)
- (写真24)玉津島明神(福島県)
- (写真25)白河関跡
- (写真26)白河手打ちラーメン
今回は奥州に入った、ここ白河までの報告です。次は平泉中尊寺とその先を報告予定です。
記事・写真:岩﨑 和隆、HP作成:宮元
以上
写真はクリックで拡大できます。
記事が良いと思われた方は下記 いいねボタン のクリックをお願いします。















































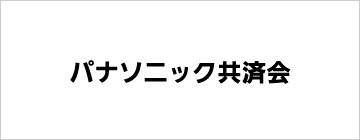


この記事へのコメントはありません。